ブログ
BLOG
こんにちは。究進塾 編集部です。
今回は基礎学力到達度テストの過去問から、文法・熟語対策について解説します。<高校3年生9月 大問2(A)>を例に、学習ポイントについて見ていきましょう。
💡この記事を読んでわかること💡
・出題の傾向
・文法についてどう学んだらいいのか
☆今回の解説は、あくまでも傾向を見て対策について解説するものです。細かい文法の説明などはしないので、わからない単語・文法があった場合、ご自身で調べるなどして解決するようにしてください。
はじめに
こちらの記事は、究進塾の講師、細田朗先生の解説動画を参考に作成しています。音声を聞ける環境の方はぜひ動画をご覧頂き、細田先生の講義の雰囲気を掴んでいただければと思います。
動画紹介
【究進塾】基礎学対策チャンネル
【日大付属】高3-9月 基礎学力到達度テスト 英語 大問2(A)「文法・熟語」対策(所要時間:13分35秒)
早稲田大学教育学部英語英文学科卒。 第二言語習得法に基づいた音読を重視した英語指導法が特徴。TOEIC945点。英検1級取得。日大付属生への指導経験も豊富で基礎学対策に精通した講師です。☆基礎学対策の詳細はこちら
【日大付属高校-基礎学対策】2024年夏期講習(集団授業)開催のお知らせ
※こちらの講座は終了しました。ありがとうございました。
今年度も、9月の基礎学にむけて夏期集中講座の開催が決定しました!

詳しくはこちら!
大問2(A)の解説
形式:4問(問11~問14)
この形式は例年一緒です。1問ずつ見ていきます。
| (A)次の英文の” ”に入れるのに最も適切な語を①~④から1つ選び、番号で答えなさい。
問11 問12 問13 問14 |
問11
選択肢を見ると「 wherever, whenever, whatever, however 」とありますが、これらは全て複合関係詞と呼ばれる、高校2年生ぐらいで習う文法です。文法と言ってはいますが、意味を知っていて文脈に沿うものが選べれば解ける問題です。(A. ③whatever)
問12
「only to do」という不定詞の定型表現を知っていれば解ける問題です。これも高校生で習うぐらいのレベルです。(A. ④only)
問13
「far from」という表現、これは熟語です。これも知っていれば解ける問題です。(A. ④far)
問14
「with」が入ります。「付帯状況のwith」と呼ばれる文法を知っているかどうかが解答のポイントです。これも高校1年生ぐらいで学ぶような内容です。選択肢を見ると他を入れようがないので、付帯状況のwithを知っていれば解けるという問題です。(A. ①with)
出題の傾向
①難易度
難易度は高1~高2レベルです。
複合関係詞:高2ぐらい
付帯状況のwith:高1ぐらい
少なくとも高校生の早い段階で学ぶようなもので、全体として高1~高2ぐらいのレベルです。英検で言うなら準2級、高くても2級ぐらいのレベルです。
どちらにせよ、高校の基礎的な部分の内容からの出題なので、難易度としては高いということはありません。かなり基本的・基礎的な内容が出されています。
②出題範囲の特徴
この試験の特徴は、「幅広い範囲から浅く広く出題されること」です。過去問を見ても、特定の狭い範囲に絞って出題されることはほとんどありません。つまり、「ここだけ勉強すれば大丈夫」というような限定的な対策は難しいと言えます。
しかし、範囲は広いものの、難易度は高くありません。文法を深く掘り下げて理解することも大切ですが、完璧でなくても満遍なく学習しておけば十分対応できるのが、この試験の傾向です。
③ シンプルな問題が多い。だからこそ「知っているかどうか」が勝負。
基礎学の文法問題には、ある大きな特徴があります。
それは、「知っていれば解ける」シンプルな出題が中心だということ。
たとえば今回紹介した大問2(A)の問題を見ても、選択肢の中に紛らわしい選択肢があるわけではなく、正しい知識があればすぐに答えられる問題ばかりです。
🧠 大学入試との違いは?
一般的な大学入試では、選択肢が巧妙に作られていて、
「うーん…こっちもアリかも?」と迷ってしまう問題が多く出題されます。
しっかりした文法理解がないと引っかかってしまう、そんな精密な問題も多いですよね。
ですが、基礎学は違います。
本当に基本的な文法や語法が問われていて、そこに難解さはありません。
✅ つまり、基礎学の文法問題は…
素直な問題が多い
紛らわしい選択肢はほぼない
正しい知識があれば確実に得点できる
だからこそ、「なんとなく知ってる」ではなく「ちゃんと使える知識」を持っているかどうかが重要です。
逆にいえば、日々の学習で基礎をしっかり固めておけば、確実に得点源になるのがこの大問2(A)のような文法・熟語問題なのです。
学習のポイント
文法学習のポイントは3つあります。
①わかるより、できるを目指せ
文法学習する人が陥ってしまいがちな1つの落とし穴として、文法をわかったことで満足してしまうことがあります。例えば、
|
学校で、文法の関係代名詞の授業を受けた |
こうした経験はありませんか。このように、文法を理解したことによってすっきりしてしまい「よし今日の英語学習はこれで終わり!」と終わってしまう人がすごく多いです。
ですが、考えてみてください。この状況、結局、英語を何もやっていませんね。文法をやってはいますが、実際にその文法を使って何かできるようになったわけではありません。文法というのは、いわば英語のルールみたいなものであり、この段階では「ルールを理解した」というだけで、実際には何もできるようになっていないんです。
こういうことが英語学習、特に文法学習では起こってしまいがちです。なので文法学習をする上での目標は、あくまで英語ができるようになること。これを目指してください。
文法は英語ができるようになるための手段であって、文法を学習することそのものがゴールにならないように気をつけてください。
②実践経験を積もう!
英語が「できるようになる」ためには、実際に英語を使う経験=実践がとても大切です。
これはスポーツと同じ。たとえば、サッカーのルールを読んだだけで、いきなり試合で活躍できる人はいませんよね。
「オフサイド」というルールも、言葉で説明を聞いても、最初はイメージがつかみにくいもの。でも、試合や練習を重ねるうちに「こういうときがオフサイドなんだ」と体でわかってきます。
英語も同じです。
文法を本や動画で学んでも、それだけでは「使える英語」にはなりません。
読んで、聞いて、書いて、話して――そうやって英語にたくさん触れることで、少しずつ「こういうときにこの文法を使うんだな」と自然に身についていきます。
だからこそ、文法書を読むだけで終わらせず、
実際に英語を使う機会を積極的に作ることが大切なんです。
小さなことからでいいので、英語を「使う」ことを意識してみましょう!
③ 最初から完璧を目指さなくていい。むしろ、その方がうまくいく。
文法を勉強する人は、大きく2タイプに分かれます。
-
「文法は苦手…できればやりたくない!」というタイプ
-
「どうせやるなら全部しっかり理解したい!」というタイプ
このうち、しっかり理解したい派にありがちなのが、
最初から全部を完璧に理解しようとしすぎてしまうことです。
でも実は、文法って一度で完璧に理解するのは難しいものなんです。
📘 文法は“後からわかってくる”もの
たとえば中学校で習う「SVOC」の文型。
最初に習ったとき、「Cって何?」「補語ってどういうこと?」とモヤモヤしませんでしたか?
でも、高校でたくさんの英文に触れていくと、
「あ、これが“補語”ってことか」
「この語順になるのは、こういう理由なんだな」
と、後から自然に理解できるようになっていきます。
🔑 最初から完璧じゃなくていい。少しずつ、体で覚えればOK
もちろん、「ちゃんと理解しよう」という姿勢はとても大切です。
でも、最初から100%理解しようとする必要はありません。
文法は、実際の英文を読んだり書いたりする中で、
少しずつ「使いながら覚えていく」ものです。
だから、文法を勉強するときは、
-
最初から全部を理解しようとしすぎない
-
完璧じゃなくても、「なんとなく」でスタートしてOK
-
たくさんの英文に触れながら、少しずつ納得していく
このくらいの気持ちで取り組んでいく方が、結果的に力がつきやすいですよ。
おわりに
今回の解説は以上です。究進塾では基礎学の予想問題や過去問を使ったりしながら基礎学対策を行っております。受講をご検討の方、ご質問や気になることがある方は「無料体験授業をご希望の方」からお気軽にお問い合わせください。
究進塾 編集部
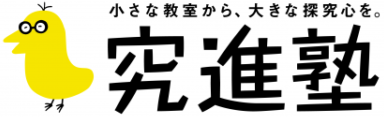
究進塾は、「学問の楽しさを伝え、結果を出す喜びを体験してもらうことで塾生の人生を豊かにしたい」という考えから、学習に役立つ情報や学習のコツなどを発信しています。
マンツーマン個別指導専門で、大学入試や大学院入試、単位取得、日大基礎学力テスト対策など、多様なニーズに対応。









