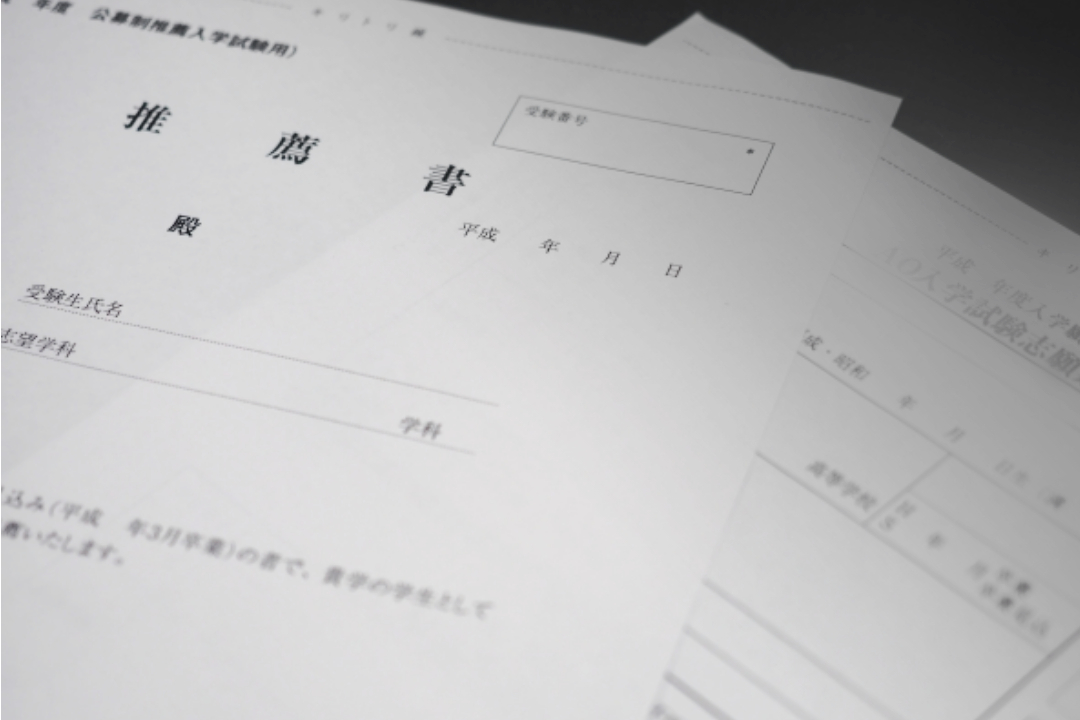ブログ
BLOG
こんにちは。究進塾 編集部です。
今回の記事は、江口先生「電磁気学 第2回」の続きです。電場、電位について解説します。
江口先生の動画解説
はじめに:当記事は、動画で解説をしている内容をご紹介していますが、音声を流せる環境にある方はぜひ動画をご覧いただき、江口先生の授業の雰囲気も一緒に掴んでいただければと思います。
江口和弘講師:「【大学物理】電磁気学 第2回 – Coulombの法則, ベクトル解析の基礎, 電場, 電位,立体角」(所要時間 1:01:49 )
この記事に該当する箇所:29:03~46:20(分数をクリックすると開始分数箇所から別窓で開きます)
電場(電界)
まず最初に、電場とは何か、どういうものかについて勉強していきます。
電場、電界という言葉
電場は別の言い方で「電界」と言うこともあります。必ずしもではありませんが、物理を専門とする方は「電場」という言い方を使わせる方が多く、電界という言葉は工学系、特に電気工学系の方が使われます。電場と電界は、言葉は少し違うのですが、同じことを言っています。
電場とは何か
電場とは、これは読んで字の如しで「静電気力が作用している場所のこと」を指します。空間電気力がある場所のことを、電場と言っているわけです。イメージのわかりやすい例として、風速を表している天気図を見てみましょう。

こういう場所があるとします。このとき、図のように「風の向き」が書いてあります。つまりこれは一応、一種のベクトルになっているので、この図の中の色々な場所で、
「この場所ではこっち向きにこういう大きさのベクトルを持っている」
「ここの辺りはこっち向きにこういう大きさのベクトルを持っている」
と言うことができます。
このように、ある場所に対して、ベクトルの量(大きさと方向)が場所ごとで決まっているものを、一般的に「ベクトル場」といいます。
つまり電場というのは、ベクトル場と一緒です。電場は、ベクトル量(方向と大きさと両方)を持っている量なので、ベクトル場と言います。
電場の強さ、大きさ
では、電場の強さ、大きさはどう定義されるのかということを解説していきます。1 [C](クーロン)の電荷を持ってきたとき、そこに作用する力のことを電場の大きさと定義します。これは定義なので決め事です。
なので、ここに1 [C]の電荷を持ってきたとき、この電荷に\(F\)という作用力が働いた場合、この力そのものが電場になるわけです。当然、1 [C]に働く電場がEなので、ここにq [C]を持ってくると、q倍の力が働くわけです。式は次のようになり、これは高校の物理も出てくる量で、非常に重要な式です。
\(E = \frac{1}{4πε_0} \frac{Q}{r^2} \frac{r}{r} \)
では、電場の大きさを具体的に書くとどうなるのか説明します。電場は何が作るのかというと、電場は力の一種なので、前述のクーロンの法則でやったように、電荷が作るわけです。なのでクーロンの法則を使います。

片方の電荷をq [C]とし、電場を求めるので右側の電荷を1 [C]としてクーロンの法則を書いてやると、次のような式になります。
\(E = \frac{Q}{4πε_0r^2} \)
なので、ここに1 [C]を置いてこれに力が働いてるわけですから、このときの電場は\(E = \frac{1}{4πε_0} \frac{Q}{r^2} \frac{r}{r} \)のように定義します。そして大きさだけで言うと\(E= \frac{Q}{4πε_0r^2}\)です。
クーロンの法則でも述べましたが、\(\frac{r}{r}\) は単に向きを表してるだけのベクトル量です。
これは後で点電荷の項でも出てきますが、非常に重要な基本的な量になりますので、特に覚えておいてください。
| まとめ 🔵電場:静電気力が作用している場所(空間) 🔵電場の強さ:1 [C]に作用する静電気力 🔵電場はベクトル(大きさと方向をもつ) 電場の強さ :\(E = \frac{Q}{4πε_0r^2} \) 電場の大きさ:\(E=\frac{Q}{4πε_0r^2}\) |
静電気力によるポテンシャルエネルギー
次に、静電気力によるポテンシャルエネルギーを考えます。まず復習として、力がする仕事というのは何だったのかということを確認しておきます。
 重力による位置(ポテンシャル)エネルギーmgh =基準点まで動かすときに重力がする仕事 |
この図にあるように、力\(F\)があって、それで変位\(S\)を動かしたときの力は、\(F\)と\(S\)の内積で定義されます。これは力学で出てきた話です。
例えば「位置エネルギー、高さ\(h\)のところにある質量\(m\)の物体の位置エネルギーは\(mgh\)である」ということはご存知かと思います。
この位置エネルギー、つまりポテンシャルエネルギーは何なのかというと、1hにある物体\(m\)を基準点、この場合は下に書いている地面にあたりますが、そこまで動かすときに重力がする仕事を「位置エネルギー=重力によるポテンシャルだけでいい」としているわけです。したがって「mgh」となります。
これと同じことを静電気力に適用します。先ほどやったのと同じように、電場\(E\)が働いてるところに電荷\(Q\)があると、\(F=qE\)という力が働く、とします。それを変位\(ds\)を動かしたときの仕事が\(F\)と\(ds\)の内積になるので、これを今考えている点から基準点まで足し合わせます。静電気の場合は基準点を無限大に持っていきますので、無限大まで全部足し合わせる、つまり積分すれば、この点にある電荷qの位置エネルギーということになるわけです。
| ある点Aから基準点(∞)まで電荷を動かすときに静電気力がする仕事 \(U_A \displaystyle \int_{A}^∞ qE・ds = -\int_{∞}^A qE・ds\) 重力による位置(ポテンシャル)エネルギー =基準点まで動かすときに重力がする仕事 |
なので式で表すと、\(qE\)と\(ds\)の内積を取ったものを、\(A\)から無限大まで積分します。そして、積分区間を上下入れ替えるとマイナスがつくので、マイナスの無限大から\(A\)まで\(qE・ds\)を積分します。
これが、電荷qがある点でのポテンシャルエネルギーということになります。
電位
電位
1 [C]の電荷を、基準点(∞)まで動かすときに、静電気力がする仕事。単位は[V]。 \(Ex = – \frac{∂V}{∂x}:Ey = -\frac{∂V}{∂y}:Ez=- \frac{∂V}{∂z} \) |
電位の定義は次のように考えます。
先ほどはq [C]というのを考えましたが、今度は「1 [C]の電荷を基準点まで動かすときに静電気力がする仕事」を電位と定義します。なので、先ほどの電荷\(q\)のところを1 [C]と置き換えればいいわけです。そのとき、力は\(E×1\)で電場そのものになります。これを変位\(ds\)に沿って積分していきます。
この点から、基準点である無限大まで積分していくので、\(V\)は\(E\)と\(dx\)の内積を、今考えている\(A\)点から無限大まで積分していったものになります。積分範囲を入れ替えると、マイナスの無限大までです。
これが電位の定義です。電位の単位は、\(V\)(ボルト)で表します。
まとめると、\(V=\)「\(E\)を積分したもの」になるので、逆に\(E\)は電位\(V\)の傾き、\(∇\)(ナブラ)、演算子をかけたものになります。そして成分で掛けると、先述の式に書いてある\(x\)成分は\(V\)を\(x\)で微分したもので、\(y\)成分は\(V\)を\(y\)で微分したもの、\(z\)は\(V\)を\(z\)で微分したものになります。で、\(V\)が\(-∞\)の\(A\)という形になっているので、微分したものを前にマイナスがつきます。
こういう形で、電場と電位の関係が表されるわけです。
電位差
次に電位差を考えます。
A点とB点の電位の差を考えますが、これは単純に、\(A\)点と\(B\)点の電位の引き算をすればいいわけです。電位の定義に従って、次のような式になります。
\(V_A – V_B = – \displaystyle\int_{∞}^A E・ds – (- \displaystyle\int_{∞}^B E・ds)\)
\(E\)を\(-∞\)から\(A\)まで積分したものから、\(-∞\)から\(E・ds\)を積分したものになります。これを計算、積分範囲を入れ替えて計算するとこのように変形できるので、結局マイナスがついた形で\(E・ds\)を\(B\)から\(A\)にまで積分したということになります。
マイナスがついたので、この場合は静電気力に逆らって、1クールの電荷を\(B\)から\(A\)まで動かしたときの必要な仕事、これを「\(AB\)間の電位差」というふうに表します。
\(\displaystyle\oint_C E・ds = \displaystyle\int_{A}^A E・ds = V_A – V_A = 0 \)
それから上記のように、任意の曲線=閉曲線CをA点からぐるっと一周回したことを考えます。すると\(A\)から\(A\)まで積分することになります。積分すると\(V_A – V_A\)なので当然\(V_A\)の電位は同じですので、1周ぐるっと回してしまうと、積分したものは0になる、ということになります。
そこで、ストークスの定理を思い出してほしいのですが、これは面積分と線績分を変換する公式でした。
Stokesの定理 \( \displaystyle \int_{S} ∇× A・ds = \displaystyle \oint_{C} A・ds \)
で、これを\(E・ds=0\)、積分0に適用すると、この線績分、周回積分を面積分に変えることができます。\(E\)の回転\(∇\)、つまり外積の\(E\)と\(ds\)、これはこの微小面積を表した面積のベクトルですが、これが0ということになります。ということは積分の中身が0ですので、\(E\)のローテーション(回転、\(∇\))、つまり外積の\(E\)は0になるということになっています。
\(\displaystyle\oint_{C} E・ds = 0\)
\(\displaystyle\int_{S} (∇×E) ・ds = 0\)
![]()
この式は、「電荷がない静電場の場合は必ず成り立つ」という式になります。
🔵点電荷による電場と電位
では具体的に、一番重要になる点電荷による電場、電位がどうなるのかということを考えてみます。
\(E = \frac{1}{4πε_0} \frac{Q}{r^2} \frac{r}{r}\)
\(E =-∇V\)
点電荷\(Q\)があったときに、電場は上記のように \(\frac{1}{4πε_0} \frac{Q}{r^2} \)、これが大きさです。\(r\)分のベクトル\(e\)と書いてあるのは、単にこれは\(r\)方向のベクトルを表してる量ですので、このような形になります。
そして電位は次のようになります。
\(V = \frac{1}{4πε_0} \frac{Q}{r}\)
\(V = – \displaystyle \int E・ds \)
これは高校の物理でも出てくる公式そのものです。先ほどやったように、\(E\)と\(V\)の関係は、電場\(E\)は\(V\)の傾きをとったもの、\(∇\)を演算したものだから、逆に電場から電位を求めるときはこれを積分してマイナスをつければいいということになるので、\(E = -∇V\)のような式になります。
具体的に関数的に書くと、これは電位を取って\(\frac{1}{r}\)、いわゆる反比例の式になっているので、電荷が\(Q\)のときは以下の図の赤線のような曲線、青の場合は青線のような曲線になります。

そして\(r\)を無限大に持っていくと、電位は0になるわけですが、これが電位が0になるので先ほど無限遠点を基準点、つまり電位を0になる点を無限遠として定義したわけです。
それから、電荷\(Q\)、1個だけを考えたわけですが、複数の電荷があった場合は、これは完全に重ね合わせが成り立ちます。足し算してやればいいということになるので、それぞれの電荷からの電場、電位を足し算してやればいい、和をとってやればいいわけです。ただし、電位の場合はこれはスカラー量なので単純に数値を足し算すればいいのですが、電場はベクトルなので、足し算はベクトルでやる必要があります。この点だけ注意が必要です。
| まとめ ・複数個(\(n\ 個))の点電荷による電場と電位 ・重ね合わせが成り立つ\(E =\displaystyle \sum_{i=1}^{n} E_i = \frac{1}{4πε_0} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{Qi}{r_i^2} \frac{r_i}{r_i}\)\(V = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} V_i = \frac{1}{4πε_0} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{r_i}\) |
🔵連続的電荷分布による電位
🔵線分布(λ [ C / m ])
点電荷のことを考えましたが、今度は「連続的に電荷が分布してるときに、電位をどう考えるか」ということです。
まず線状分布ですが、下図のように、曲線に沿って電荷が一様に存在しています。

線分布、線密度を\(λ\)として、1m当たりの電荷をλ[C/m]としておきます。微小な距離\(ds\)があり、ここには\(λds\)という電荷がある、ということを考えます。するとこれを点電荷と考えて、これによる電場を考えればいいということになります。それを、\(A\)から\(B\)まで全部足し算、つまり積分してやれば求められることになり、\(V\)は以下の式で計算できるということになります。
\(V= \frac{1}{4πε_0} \displaystyle \int \frac{λds}{r}\)
🔵面分布(σ \([ C \ m^2\) ]
面分布も同じように考えることができます。

非常に小さい面積要素を考えると、ここにある点\(σdS\)となるわけですから、ここで書いてる緑の面全部で積分してやれば、電位が求まるということです。
\(V = \frac{1}{4πε_0} \displaystyle \iint \frac{σdS}{r}\)
🔵体積分布(\(ρ [ C / m^3 ]\))
さらに体積分布してるときも同じです。

微小なところの体積要素\(dv\)を考えると電荷量\(dv\)ということになるので、これを全部足し算してやれば、この閉曲面内にある電荷による電位が求まります。
\(V = \frac{1}{4πε_0} \displaystyle \iiint \frac{ρdv}{r} \)
電場は \(E = – ∇V\)
それで電位が求まると、電場はこれを微分、いわゆる傾きを取ってやることにより電場を計算できる、ということになります。
立体角
少し話は変わりますが、立体角という概念をここで導入したいと思います。
立体角を考える前に、一般的な角度、普通の角度ということを考えます。
🔵角(平面)

このような半径Rの円を考えると、角度\(θ\)、この\(θ\)はラジアンで表していますが、\(l=rθ\)という関係があるので、角度というのは、弧の長さ÷半径で定義しているわけです。これを空間に拡張し、立体角を考えます。
🔵立体角(空間)

平面では円で考えたので、これを球に拡張します。そうすると、今まで線 \(l\)だった線がこの球面のSという面積になり、これを\(r^2\)で割ったものを立体角というふうに定義します。単位は\(Sr\)と書いて「ステラジアン」と読みます。物理的には無次元量です。
🔵立体角(一般)
球面で考えましたが、一般に\(dS\)という微小な面積要素があったときの立体角はこれの法線方向をとって内積を取ればいいわけです。

\(δΩ = \frac{δS cos θ}{r^2} = \frac{δS・r}{r^3} \)
この微小立体角は、\(\frac{δS cos θ}{r^2}\)、いわゆる\(\frac{δS・r}{r^3}\)の内積、と計算できることになります。
この球面の方から見てもわかるように、平面の場合は1周回った角度が\(2π\)でした。立体角の場合は全体を回るわけですから、\(4πr^2\)で球の面積、表面積が\(4πr^2\)になるので、それを半径で割ると\(4π\)、全方位を見渡したときの立体角は\(4π\)になります。平面の場合は、1周ぐるっと回ったときの角度は\(2π\)、これが立体角です。この後、これを使っていこうと思いますので、ここでちょっと紹介しておきます。
<続きます>
関連記事:【大学物理】電磁気学シリーズ
第1回 – 静電気、帯電、静電誘導、誘電分極 –
第2回-【大学物理】電磁気学 第2回① – Coulombの法則
第2回-【大学物理】電磁気学 第2回② – ベクトル解析の基礎(電場、電位に必要な数学)
第9回 – 静電容量(コンデンサー) –