インタビュー
INTERVIEW
ゆうたろう様合格インタビュー (3) 医学部2次試験のヒント
<続きです>
エンジンがかかってからの勉強
並木:エンジンかかってからは、いいペースで進めたんですか?
北田:そうですね。ただ、はっきり言ってしまうと、ゆうたろうくんは「自分のやりたいことをやる」んで。「本当はそっちじゃなくて、こっちをやってほしい…」みたいなことはありました。
例えば、やっぱり医学部なので、過去問も1校や2校じゃないですよね。なので「今はちょっとこっちの過去問をちゃんとやりたい」みたいなことがこっちとしてはあって、それを話すんですけど「わかりました!じゃあ」って授業中は言うけど、実際そうならないっていう。ある程度は意向を汲んでくれるんですけど、やっぱり「自分はこう!」っていう方を大事にするので。

北田:そこに対して僕も「いや、そうじゃなくてこっちを…」っていうことをしないようにしよう、と。だから結果として、過去問対策も均一じゃなくて。「ここはちゃんとやったけど、ここは割と薄かった」みたいなところはもちろん出てきちゃったんですけど、ただ、ちゃんとこうやるところは、きちんとやってた。
高3から頑張った子の“落とし穴”と、本人の癖
北田:学習の変な穴みたいなのを埋める作業は、最後までずっとやりましたけどね。本当に中1の領域とか。「これ、中1でやる内容だから、ちゃんと教えなきゃ駄目なんだ」っていうことが結構あって。高3とか、そのぐらいになってから馬力込めてすごく頑張った子って、すごい土台のとこが変に抜けてたりするんですよね。それが直接失点に繋がるっていうケースが意外と多くて。なのでそういうのを最後まで詰めながら。
さっきも話したように、ミス分析とかそういうところはすごくできるようになってたんですけど、ただやっぱり彼の「“野性”の癖」っていうのが最後まで残っていて。知識とか考え方は、ここで勉強したものを冷静に使えば、去年とは違う形で正しく読めるんですけど。

北田:思考の癖として、おそらく頭の回転が早いせいでパッと見たときにバーっといろんな思考が出てきて、そこに従来の根拠なしの「こうじゃないか」っていうものがすごく強く出ちゃって、変に誤読をして変に間違っちゃうっていうのは、結構最後のギリギリまでそういう失点があった。そこの「こういうときどうするんだっけ?」っていう、ぱっと出ないときの対処法みたいなのは最後までやりましたね。
北田先生に習って変わったこと
並木:ゆうたろうくん的には、北田先生に習っていくうちに「この辺変わったな」みたいなことは何かありますか。
ゆうたろう:北田先生に習って、一番はさっき言ってた「野性」が理性寄りになったり。
北田:「野性の上に理性も入った」っていう(笑)
ゆうたろう:そうですね。(笑) 野性から理性の、ちょうど中間ぐらいの。ちょうど混在してるぐらいにはなったっていうのが一番ですし。一番記憶に残ってるのは、1月、2月、3月、4月とか、月を英語で言えなかったりとか、もう一番最初の宿題が…。(笑)
北田:言うんだそれ。(笑)
ゆうたろう:(笑) もうそんな感じで、本当に「え?それ知らないの?」っていうことがあって。例えば「夕食」が「dinner」の他にもう1個あるのを、そのもう1個の方が出なかったりとか。そういう感じで、本当に基礎すぎるものが抜けてたりとか、自分でも「それ聞いたことないですよ」っていうことが「それ、定番なんですね…」みたいな。そういうのが抜けてたりして。
やっぱりそれって自分でやってるだけじゃ埋まらなかったり、高3ぐらいから英語は頑張ってたんですけど、やっぱり変なところが抜けてたり、地盤とか基盤がボロボロだったっていうのが。1年通して考えると、気づかないことを気づかせてもらったりしたのが大きかったですかね。
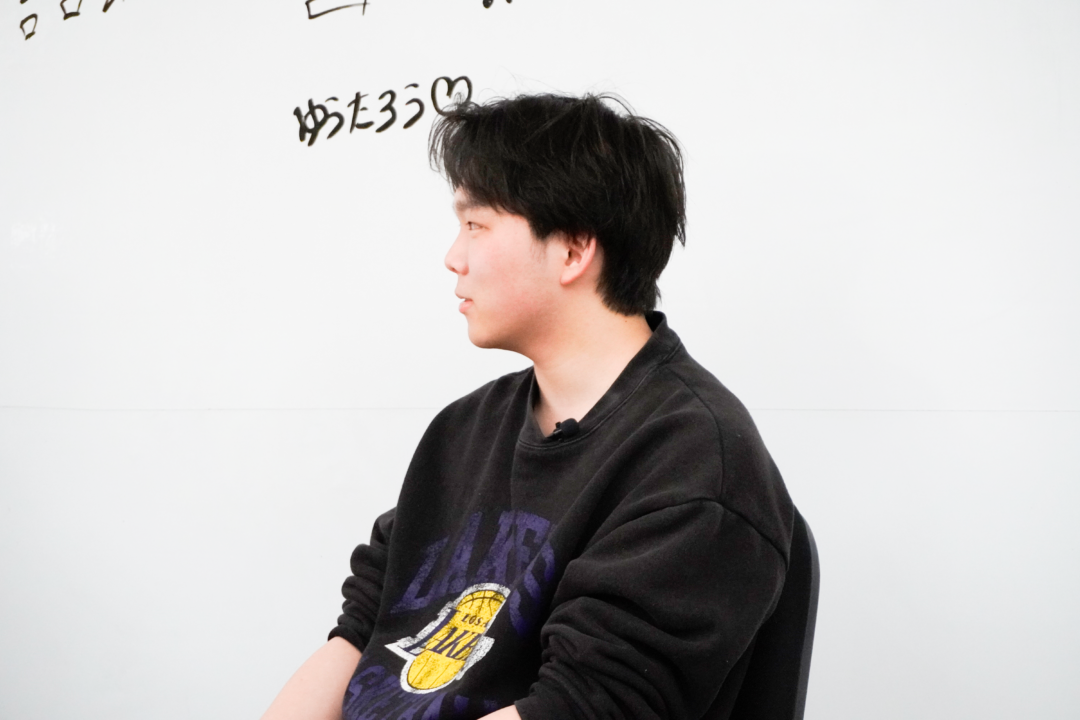
北田:自分で気づくの無理だもんね、ああいうものは。
ゆうたろう:そうなんですよね、本当に。
北田:それがね、ただ「知識がない」だけだったらいいけど、結構それが原因で失点に繋がるっていうことが多々あったから。でも、自分でできることは頑張ってたと思うんだよね。そこにプラスアルファで、究進塾に来たからできることっていうのも加わって、っていう感じだと思う。「月」が言えないで医学部目指そうっていうね。January, Februaryが言えないって、想定しないじゃないですか、こっちも。
ゆうたろう:(笑) 本当に「これ何月でしたっけ」って聞いてました。
北田:そういう発見は、随時ありました。「これができて、何でこれができないんだろう?」っていうのを。しかも、できないものが体系化されてないから、見えてきたらその都度潰すしかないっていう感じだったからね。半分面白かったけど(笑)
ゆうたろう:(笑)
医学部の2次試験について
並木:1次試験に受かった後の、2次試験ってどんな感じだったんですか。
北田:やっぱり「2次こうだったよ!」っていうのが、医学部目指してる子には「そんな感じなんだ!」って参考になると思うんだよね。
ゆうたろう:なるほど。
北田:ゆうたろうくんはね、すごいちゃんと喋れるタイプでもあると思うし。
ゆうたろう:そうですかね。ありがたいですね。
北田:「こういう経験だったよ」っていう出来事とか、思い出というか。

ゆうたろう:そうですね…やっぱり大学ごとに受験の方法とかもいろいろ違って、特色とかもありました。今年で2次試験を受けたときに、福岡大学は一対一の面接ではなく、集団面接だったりして。しかもそれ、僕一番最初だったんですよ。面接の一番最初に呼ばれて。他のグループは最初に受験者同士で話す時間があったんですけど、僕たちはもう10秒ぐらいしか話せなくて。
北田:ぶっつけ本番だね!
ゆうたろう:そうですね。しかもちょっと驚いたのは、面接とは全然違う話なんですけど、その10秒間で名前言ったときに、小学校で会った以来の、小学校の同級生が目の前にいて。
北田:え、同級生??
ゆうたろう:同級生が目の前にいて(笑)
北田:たまたま?
ゆうたろう:たまたま。本当にたまたまいて、名前言ったら「ちょっと待って、小学校どこ?」「え、〇〇だけど」「え、一緒!!」みたいな。「お前か!」みたいな。(笑)
北田:へえー。
ゆうたろう:医学部受験の2次ってすごく緊張するので。他の面接とかでも緊張すると思うんですけど。やっぱりそういう知り合いとかがいると、一気に緊張が解けたっていうのはありますね。
北田:そりゃそうだろうけど…そんなにそうそう「おぉ!」みたいなの、無いよ。(笑)
ゆうたろう:すごい確率です。(笑)
北田:それは何か…たまたま引きが強かったね。
ゆうたろう:そうですね、嬉しいハプニングでもありましたね。
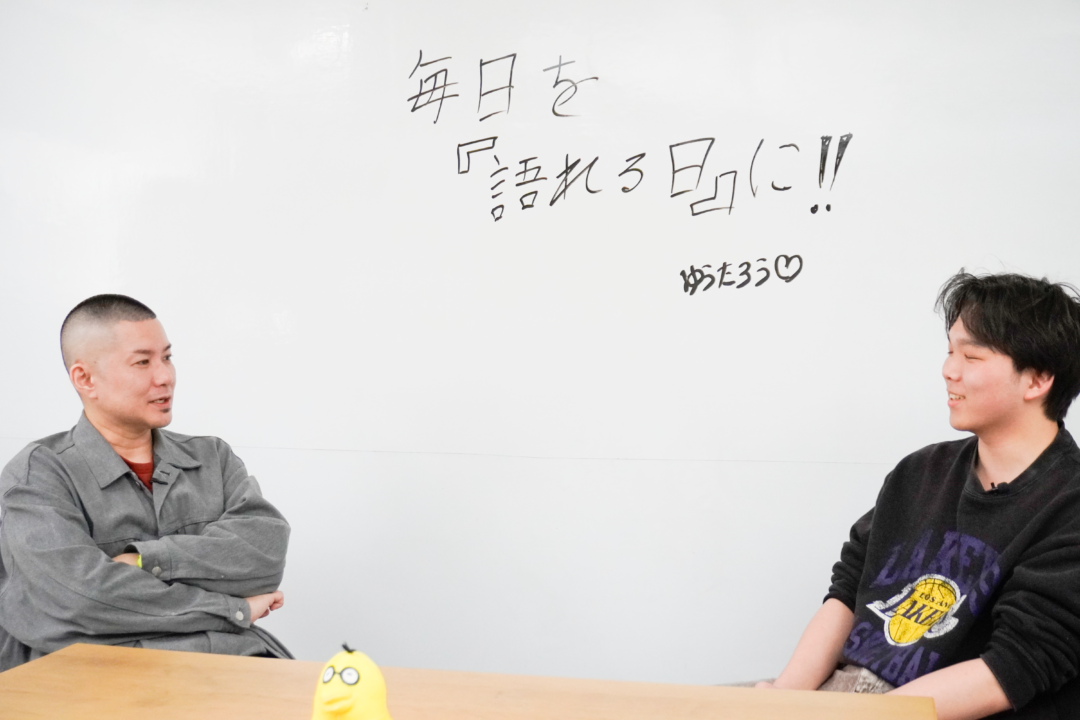
ゆうたろう:それでそのとき緊張がほぐれて集団面接に入ったんですけど、自分的には一対一の面接の方が楽だった感じがして。一対一だと、質問が先に予測出来たりしたので。例えば「自分のなりたい医師像、診療科、専攻科」とかを聞かれた際に、そこからの派生で、問題点とかは予測しやすいので、事前にそこを埋めることができるんですよね。準備ができる。
北田:逆に言うと、そうか。いわゆる医学の世界の、医療現場とかの問題点は、やっぱりある程度事前に網羅しといた方がいいっていうことだね。
ゆうたろう:そうですね。
YouTubeの活用方法
ゆうたろう:僕は、そこまで網羅してるかっていうと全然網羅してなかったんですけど。例えば最近だと、YouTubeショートとかを活用できて。例えば「直美(ちょくび)」っていう言葉があるんですけど、「研修期間が終わったらみんな美容整形とか美容外科に行っちゃう」っていう問題があったりして。
| 直美(ちょくび)の問題点
「直接、美容外科に就職すること」の略。国家試験合格、2年間初期研修修了後、一般的な診療科への臨床を経ないまま美容外科へ就職する人が増加し、年間200〜300人とも言われる。 自由診療が基本で収益性の高いこと、休暇の取りやすさが美容外科就職の魅力といえるが、基礎的な臨床経験を経ないため、患者の安全、適切な医療提供の観点で問題視されている。経験が浅いゆえの医療事故、トラブル発生のリスクのみならず、医療全体の質の低下、地域医療の医師不足の加速など、懸念されるのは個人の問題だけではない。 |
ゆうたろう:それについて語ってるYouTubeショートとかが流れたり、そういう医療に関する時事的な問題を紹介してるYouTubeショートとかがあったりして。暇なときとか、ちょっと休憩っていうときに、YouTubeショートを見ると「へえー直美なんてあるんだ」って知ると、実際に昭和医科大学の小論文試験で「直美についてどう思いますか?」っていう問題が出たりして。
「全体的な医師不足」みたいな、長年言われてきてる医師問題は多分みんな知ってると思うんですけど、最近の流行の医療問題は、YouTubeショートとかで流れてくるので、そういうSNSだけでも把握しておくと、結構ためになったりする。
北田:なるほどね。
ゆうたろう:そこは結構、一番の流行を持ってきてくれるので。だから「自分ラッキーだな!」っていうことがありました。
北田:医療業界の時事ネタみたいなものに、ちょっとアンテナを張っておいた方がいいっていう。
ゆうたろう:そうですね。ただそれが流れてきただけでも「いいね」を押しておくと、自分が調べなくても似たようなものが勝手に流れてきてくれたりするので、結構「ラッキー!」と思いながら。僕はそれをやってましたね。
北田:今っぽい。
ゆうたろう:(笑) そうですね。

2次試験できつかったのは
ゆうたろう:でも、やっぱりさっき言った集団と一対一の面接の違いで言うと、福岡大学の2次試験で、5人ぐらいで「医療過誤について語ってください」っていう試験があったんですけど。
| 医療過誤とは 医療事故は、医療行為により、患者の身体や生命が侵害されることである。そのうち、医療従事者(医師や看護師)が十分な注意を尽くさなかった、つまり医療従事者の注意義務違反(過失)によって起きたものを「医療過誤」と呼ぶ。 参考:横浜綜合法律事務所「医療過誤とは何か」より要約 |
ゆうたろう:自分たちの中で、結構話したんですよ。AIを使ったり、セカンドオピニオンについて話したり、他の人にも意見を聞くとか。3つぐらいの観点から話したり、チームワーク医療とかについても、いろいろ話したんですけど、その場で課題をパッと言われてパッと考えてるから、やっぱりみんな止まって誰も喋れなくなったりとか。話していくうちに話題が尽きちゃったりして。大体30分ぐらいだったんですけど、1回完全に止まって、静寂の時間が一瞬あったりしたりとか。
北田:グループ討議が30分?
ゆうたろう:30分もあったんです。本当に長くて。自分たちも「話しきったよね」って思ったときに、「あれ、いつ終わるんだろう…」と一瞬思って。それでこれはやばいと思って僕が「じゃあ、自分たちが出した問題について語ってみる?」と話したんですけど、やっぱりそのときが一番もうヒヤヒヤしましたね。
北田:口火を切ったんだ。
ゆうたろう:そうです。もう静寂っていうのが…自分たちとしては話し切っちゃってるせいで全然出てこなかったりして、「もうやばいどうにかしないと」って。そのときが、心の中が「もうやばいやばい」みたいな感じでしたね。やっぱりそこが一対一とは違う、集団の怖さっていうのはありますかね。
北田:でもそこに切り込めたっていうの、すごいね。だってそれゆうたろうくんが何も言わなかったら、なんかよくわからない静寂がそのまま続いたかもしれない。
ゆうたろう:そうですね。とりあえず「やばくなったらどうしようかな」っていうのは、ちょっとだけ考えてはいたので。「30分」って聞いた瞬間に「絶対話もたないやん」と思ってたから。
北田:長いよね。
ゆうたろう:本当に長いです!「どんだけ話しても20分ちょいしか持たないよ!」と思って。で、話しながらみんなで「〇〇さんどうぞ」みたいな感じで話したけど、自分の番じゃないときには話を聞きながらも自分の中で「次、出てきたらこういう話題したいな」とか、「こういう話題で突っ込むのもありだな」っていうふうに考えながら聞いてたので。そうなったときに「よし!俺はまだ言えるわ」と思って。自分から発言できたのはそれぐらいすかね。でも、本当怖かったです、静寂は…。

北田:逆にいえば、グループトークっていうのは自分が喋ってないときに準備する余裕があるっていうことだよね。
ゆうたろう:結構ありますね。
北田:それこそ一対一とかだと、直で全部自分にくるからさ。もうその場で言わなきゃいけない。
ゆうたろう:はい。
並木:集団の面接の練習って、してないですか。
ゆうたろう:全くしてないです。
並木:「慣れてるな」みたいな人いました?
ゆうたろう:自分のところには、さっき言った小学校の同級生は慣れてそうだなって感じはしましたね。「最後にまとめてください」って言われたときも、率先してまとめてくれたりとかして。「この3つにしたいんですけど、みなさんどう思いますか?ちょっと変えたいところとか、言いたいことあったら。何かありますか?」っていう感じで、いい感じに最後のまとめ役とかも上手いなと思ったので、そこは慣れてるなってちょっと思いました。
北田:司会役みたいな部分だね。
ゆうたろう:「司会役を作るな」と言われたんですけど、最後のまとめのときに「どうしようかな」ってみんなが考えているときに提案をしてくれたりして。その友達の、そこはすごいなと思って。
北田:司会を作るなって言われたの?
ゆうたろう:そうです。誰が司会とかはなくって、自由に話し合ってくださいっていう。

並木:逆に、あんまり喋れない人もいました?
ゆうたろう:自分たちの中では、最初に一番端の子が喋ったんですけど、そうやったら「順番に喋っていきますか」って最初に5人全員話して、そこからみんな話していくっていう感じになって。「どう思いますか?」みたいな言葉を投げかけたりもして。あんまり誰かが喋ってなくて、誰かがめっちゃ喋ってるみたいなことは、自分のグループはなかったですね。
北田:バランスよく。
ゆうたろう:バランスよく話したと思います。それはもう、そうじゃないと。みんなが頑張って喋っていかないと、30分終わらないっていうのもあったかもしれないですけど。
北田:チームプレーじゃないと持たないってことだね。それはだいぶ、個人の面接とは違う点かもしれないね。
<続きます>





