インタビュー
INTERVIEW
I様 合格インタビュー②
| 【インタビューにご協力いただいた方々】 I様:2025年度入試にて、千葉工業大学創造工学部デザイン科学科に合格。 堀先生:I様の物理を担当した講師。 並木塾長:究進塾の塾長。 *以下、敬称略。 |
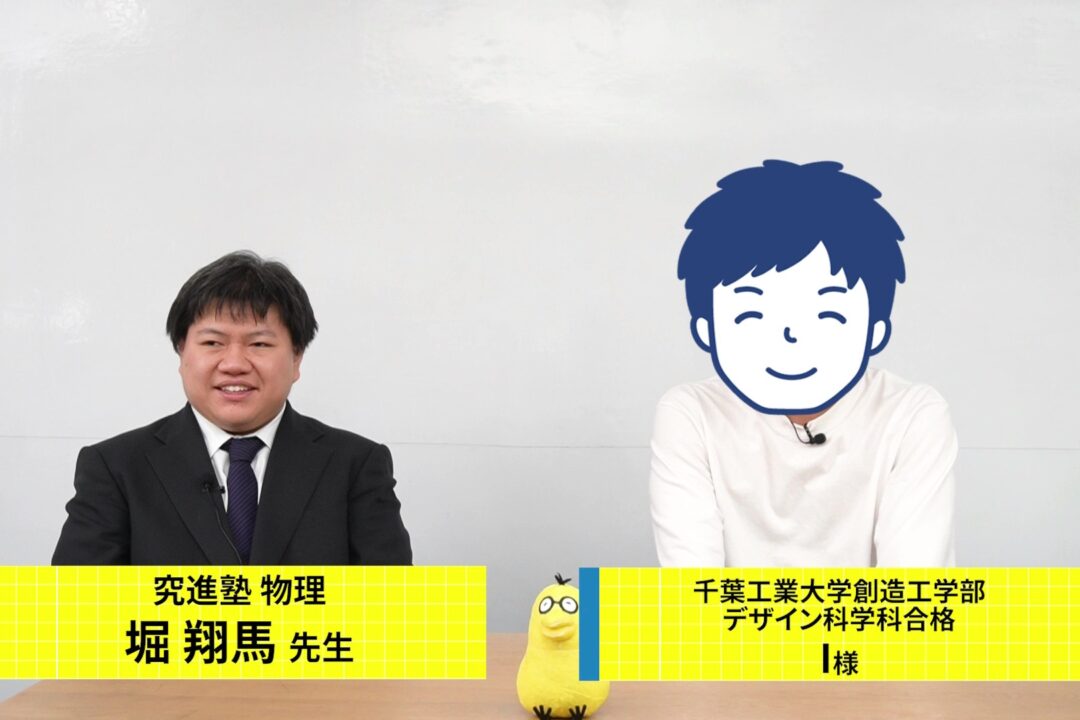
体験授業でのお互いの印象について
並木:体験授業のお互いの印象について教えてください。
I:話しやすい先生だなと思いました。
堀:それは良かったです。
並木:堀先生は最初の体験授業でお会いしたときの印象、覚えていますか?
堀:結構物理に対して苦手意識があるということをしきりに言葉の端々で言ってくれてはいたんですけど、いざ問題に着手させてみると、意外と手が動いたなという印象があります。苦手な意識や、勉強をうまく器用にこなせないという意識の方が先行してるのかなと思ったので、実践の中で正しいアプローチを磨いていけば積極的に勉強はしていけそうだと体験授業のときに思いました。
苦手科目の乗り越え方
並木:物理は一番苦手な苦手科目でしたが、どのように乗り越えたのですか?
I:堀先生はノートを取らせるタイプの勉強法だったので、何回も参考書をやりながら、授業時に取ったノートを振り返りながら進めていました。そこでなんとか物理は克服できたところがあります。
堀:ノートを復習することが自己学習の中で多かったということですか?
I:はい。
堀:なるほど。普段から板書して、板面でビジュアルで考えさせて理解させることは意識していますが、授業の中で考えたことをノートを見ながら振り返ることが合っていたのかなと思いますね。
使用教材について
並木:メインで使っていた教材は何ですか?
I:漆原先生の『漆原の物理(物理基礎・物理)明快解法講座』です。
並木:それを繰り返し学んだ?
堀:それをさわりとしてひと通りさらった後に、元々手持ちで持っていた別の問題集に着手してもらったり、明快解法講座の考え方をベースに、過去問に当てはめて勉強することをしていました。
並木:受講開始から受験本番まで約半年だったかと思いますが、短い期間で教えるときのポイントは何でしょうか?
堀:下手に焦って1単元あたりの学習のペースを短縮して勉強するより、大学受験の物理の中ではコアになる力学と電磁気をベースにして、余った時間をうまくやりくりして波動と熱力学を勉強するという方針で授業を進めていました。出題の範囲も力学と電磁気はかなり大きいので、そこの考え方がブレないようにというのは意識していました。
並木:全部典型問題をやるには難しいですよね?
堀:ですが、典型問題をかなり網羅的に扱ったと思います。明快解法講座がもう既に取捨選択がなされている問題教材ではあるので、それを中核にしながら行いました。明快解法講座に掲載されていない問題パターンが出てきたら、過去問をベースにしながら「こういう問題の考え方だとか型もあるんですよ」というのを授業の中で補助的に取り上げるようにしました。
過去問について
並木:過去問はいつぐらいから着手し始めましたか。
堀:10月頃にはもう開始していました。
並木:10月頃ということは結構早めに取りかかり始めたんですね。
堀:そうですね。早めに過去問を取り上げていって、その中で失点した項目、うまく解けなかったトピックがあったら、そこでまた基礎に立ち返って学習するというような・・実践とそこの典型問題の解法に戻るのを行ったり来たりという授業展開にしていました。
並木:実際に手応えを感じ始めたのはいつ頃ですか?
I:現役生は後半伸びるってよく言うじゃないですか。それが1月の後半とかで、「あ、ここってここと繋がるんだ」みたいな、点と点が繋がって分かり始めてきたのがその頃です。個人的には、苦手克服は結構遅かったかもしれないです。なんなら入試中に克服していったとか、そういうのもあったかもしれないです。
堀:そっか(笑)
並木:先生は何か感じたことはありましたか?
堀:経験するパターンの幅が多くなっていくにつれて、手も積極的に動くようにはなりましたし、質問の質も「こう考えたんですけどどうですか?」というタイプの質問に変わっていったので、自分なりの考えが徐々に組み立てられるようになっているのを感じましたね。
並木:教えるうえで工夫したところはありますか?
堀:短い期間での指導ではあったんですけど、省略したりショートカットをするっていうカリキュラム作りではなくて、ちゃんと時間を掛けるべきところにきちんと掛けるということは留意していました。例えば力学であれば図解なしに問題を解くことはできないので、図を描く場面や矢印を引く場面はちゃんと時間をかけて解説をしました。答案で確認するときも、Iさんがどこまで分かっているのか、どういう考え方をしたのか、またそこの考え方で間違っている点など修正するべきところはきちんとチェックをしました。
印象に残っていること
並木:堀先生の授業で印象に残っていることはありますか?
I:少し関係ないかもしれないですけど、先生とやっていて「物理おもしれー!」と何回も言っていましたよね(笑)
堀:そうだね(笑)たびたび問題が解けることがあるとそう言ってくれていましたね。
I:それこそさっき言ったように点と点が線に繋がったような。その瞬間、受験勉強という枠組みを超えて、物理の面白さに気付くことができたと思います。
堀:良かったです。私が覚えてる範囲で言うと、電磁気の問題で物体と棒をくくりつけてだんだん物体が落ちていくと、落ちていった分だけ位置エネルギーが減って、ジュール熱に変わってというエネルギーの保存の関係が装置全体で見えるという。
I:必ず保存されるんですよね。
堀:そうです。それが分かったときに、「おもしれー!」って言ってくれたので(笑)問題の仕組みとか構造などが分かる面白さを実感してくれていたと思うんですよね。
I:それは受験後もずっと続いていくかもしれないですね。
受験先について
並木:大学の受験先はどうやって決めましたか?
I:もともと大学受験というものが漠然としていて、本当に大学に行くべきかというところから考えていました。だから理系という選択も深く考えて選んだわけでは正直無かったです。それでも、デザインなら唯一出来そうだと思って。デザインを取り扱っている理系の大学は少なかったので、そこから絞っていって、最終的に千葉工業大学を受験することにしました。
並木:堀先生から見て、手応えを感じ始めたのはいつ頃ですか?
堀:過去問の演習の中で、11~12月頃には割と手が順調に動いてるなっていう印象はあったので、矯正するべき点は矯正しつつ、積極的に勉強できてるなというところは見ていて思っていました。別の生徒さんによっては受験が近づけば近づくほどプレッシャーのせいで手が動かないとか、課題の進捗が悪くなるとか、そういうことも起こりがちなものなんですけど、彼についてはむしろ逆に受験が近づくほど分かってきたという場面が多くなってきて、積極的に楽しんで勉強してるように見えましたね。
並木:合格できた要因は何だと思いますか?
堀:たびたび「物理楽しい」と言ってくれていたことでしょうか。1つ分かればそれが1個の喜びになるみたいな、楽しんで勉強できているのが彼の性格とマッチしている勉強スタイルだったのかなと思いますね。これが1つ1つ分かっても、ただ体力使う、集中力を使うっていうだけでエネルギー食うなという感想にだけなっちゃうと、何となく不安な要素もあって勉強を敬遠するみたいな感じの受験生もいらっしゃいます。だけど彼の場合は積極的に能動的に勉強するという行動に結びついていったので、結果的に楽しむということがキーポイントになったのかなと思います。
I:やっぱりそれこそ物理が好きになれたっていうところですかね、楽しいと思えたから勉強も捗ったと思います。
堀:本当に良かったです。
後輩へのメッセージ
並木:これから目指す後輩に向けたメッセージをお願いします。
I:物理の点と点が線に繋がる瞬間は本当に面白いから、そこまで耐えられれば楽しいものになると思うので、是非そこまでやってみたらどうかなと思います。
並木:毎日自習室に来てほとんどルーティンを変えずにやっていたというのが印象的ですが、コツコツ真面目にやるのが得意なタイプだったんですか?
I:それもあるかもしれないですけど、やっぱり環境が一番大きかったですね。塾とは関係なくなってしまうかもしれないですけど、学校の友達とアプリとかで勉強時間を監視しあえるようなものがあったり、そういう環境が大きかったかもしれないです。
並木:友達といい意味で刺激しあえたということですか?
I:そうですね、はい。
堀:違う場所だけど、ある意味で友達同士繋がって刺激しあって、その自習の空間がたまたまあの自習室だったっていう。いいサイクルですね。
堀先生からのメッセージ
並木:堀先生からI様に何かメッセージはありますか?
堀:理系の、とりわけ理工系の勉強を教えるような学校の環境だと数式がたくさん出てくるんですけど、学科がデザイン系ということだったので、おそらくその方向性から言って、口うるさく色んな数式の条件に惑わされずに、直感が冴えたものをちゃんとデザインに起こすことをする方が多分いい結果になるのかなって。私の想像ですけど。そういう感じの系統の学科なのかなと思うので、単位も取らないといけない環境ではあると思いますけど、是非色んな数式だったりにそんなに気負わずに惑わされずに、割と直感で感じたものを信じて進んでもらえるといいんじゃないかなと思います。
I:はい、ありがとうございます。
並木:どんなデザイナーになりたいですか?
I:ええー(笑)まあでも、それを知るために行くみたいなところもあるので、それはこれから見つけていきたいなと思います。





