ブログ
BLOG
他士業からの仕事の紹介って、実際どうなの?
「行政書士になっても、果たして仕事があるのか…?」 これは、受験を考えている方の多くが感じる率直な不安だと思います。 今回は、行政書士が実際にどのようにして仕事を得ているのか、特に「他の士業からの紹介」という観点で、実務経験を踏まえてお話しします。
① 弁護士からの紹介:忙しさゆえの“外注先”としての役割
弁護士は法的業務を広くカバーできる資格で、行政書士に比べて明確な上位資格と思われがちです。確かに、許認可業務も本来は弁護士自身で対応可能です。
しかし、弁護士は非常に多忙です。そのため、実務の現場では「手間や時間のかかる業務」を信頼できる行政書士に外注するケースがあります。特に、大企業からの難解かつ大規模な許認可申請(たとえば、報道に載るような特殊な案件)については、専門知識と実務経験が求められます。
また、報酬設定の制約などから「採算が合わない」業務を行政書士に任せることもあります。例えば、ある程度複雑な契約書作成など、時間をかければ対応可能な業務が該当します。
② 税理士からの紹介:相性◎で最も有望なパートナー
税理士との連携は、行政書士にとって非常に現実的かつ有望なルートです。
たとえば、建設業許可の「決算変更届」は、税理士が作成する決算書に基づいて行政書士が行う業務。このように、自然と協業が発生しやすい関係です。
また、税理士試験には民法や行政法が含まれていないため、これらを得意とする行政書士に対して信頼を寄せてくださることも少なくありません。顧問先企業からの「この申請、誰か頼める人いない?」という相談に応じて、行政書士を紹介していただくことも実際にあります。
ただし最近は、税理士が行政書士登録をし、自社内で処理する傾向も増えています。とはいえ、まだまだ営業先として最優先でアプローチすべき士業であることに変わりはありません。
③ 社会保険労務士からの紹介:意外に少ないその理由
社労士も、行政書士と業務分野が一部重なる士業です。補助金申請や一部の許認可業務などでは社労士も対応しており、経験値も豊富です。
加えて、社労士試験と行政書士試験の難易度が近いため、社労士が「自分で行政書士資格も取得して」一体的に業務を処理する例もあります。こうした背景から、社労士から行政書士への紹介はやや少なめです。
まとめ 士業ネットワークを活かすことも、キャリア設計の一部
「資格を取った後、実際にどうやって仕事にするのか?」という疑問は、試験勉強と並行して考えておきたい大切なテーマです。
私が担当する個別指導では、授業の前後や休憩時間を活用して、こういった“リアルな現場の話”もお伝えしています。書籍やネットでは出てこない実体験を、守秘義務に反しない範囲で具体的にお話しすることで、皆さんのモチベーション維持にもつなげています。
こうした「受験勉強だけにとどまらない情報提供」も、個別指導だからこそ可能なサポートだと感じています。
【執筆者】
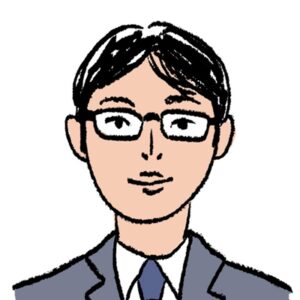
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
私立大学非常勤講師の経験を持ち、大手資格予備校で行政書士をはじめとする法律系国家資格の指導歴は約20年。
行政書士実務についての著書・論文もあります。
<塾よりひとこと>
誠実で実直な性格が特長の講師です。








