ブログ
BLOG
行政書士試験の知識は実務で通用するのか?
「合格しても、実務はまったく別物なのでは?」
行政書士試験を目指す大学生・社会人の方から、こうした不安の声をよく耳にします。
実際、私のもとにも「試験には受かったけれど、実務に不安がある」というご相談が少なくありません。
そこで今回は、行政書士試験の知識がどのように実務に活かされるのかを、20年以上の実務経験をもとに、科目別に解説します。
①憲法 ― 実務での出番は少ないが、教養として役立つ
正直に言えば、行政書士の実務で憲法を使う場面は多くありません。
私自身も、相談業務の中で憲法判例に軽く触れる程度です。
とはいえ、法的素養としての憲法知識は、依頼者に対する説明の「土台」として役立つ場面があります。
②民法・会社法 ― 実務で最も活かされる中核科目
民法の知識は、契約書作成や相続関連業務で頻繁に活用します。
たとえば、建物使用権に関する添付書類の作成では、賃貸借契約書や使用貸借契約書などを扱う場面があり、試験で学んだ内容が実務でも生きてきます。
注意すべきは、民法には借地借家法などの特別法がある点です。
こうした部分は、試験後に自分で学び直す必要があります。
会社法に関しては、会社設立業務では試験知識がそのまま活かせます。
雛形をベースにしても、十分な業務が可能です。
ただし、役員変更などの企業法務では、株主総会議事録の作成など、より実践的かつ幅広い知識が求められます。
企業法務を志す場合は、継続的な学習が不可欠です。
③行政法 ― 許認可業務の基礎として活用できる
行政手続法や行政法総論の知識は、許認可業務において極めて有用です。
例えば建設業許可申請などでは、試験で得た知識と、行政庁の手引書を併せて使えば、初学者でも業務に対応できます。
一方で、行政不服審査法や行政事件訴訟法は実務で扱うことができないため、知識を直接活かす場面は限られます。
ただし、申請却下などの際には、制度の全体像を依頼者に説明するために知識が活きることもあります。
まとめ:試験知識は「十分な土台」になる
行政書士試験で学ぶ知識の中には、実務でそのまま使えるものもあれば、補強が必要な分野もあります。
とはいえ、最近の難関化した試験に合格できる方であれば、実務に必要な追加知識は十分に習得可能です。
さらに、全国の行政書士会では、実務講座や勉強会などのサポート体制も充実しています。
「試験と実務は別物」と構えすぎずに、一歩一歩経験を積んでいけば大丈夫です。
合格後の一歩を、自信をもって踏み出してください。
【執筆者】
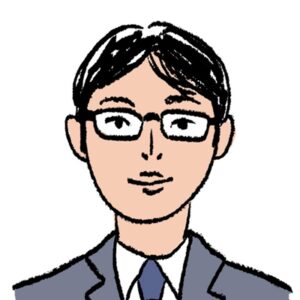
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
行政書士事務所を運営しながら、大手予備校で法律系国家試験の講師を20年間
担当してきました。法律について大学院で研究もしてきました。
「暗記より理解」が講師としての信条で、条文の理解のためならば、千年以上前
のローマの話もします。「法律の理解に資する方法を探す」ことを趣味としていて、
さまざまな文献に目を通します。蔵書は数百冊におよびます。








