ブログ
BLOG
行政書士試験の過去問教材、どれを選ぶべきか?
行政書士試験の合格に向けて避けて通れないのが「過去問演習」です。しかし、いざ書店に行くと、さまざまな出版社・予備校から異なるタイプの過去問教材が並んでいて、「どれを使えばいいのか分からない…」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、過去問教材の種類とそれぞれの特徴、そして受験生のレベル別におすすめの使い方をご紹介します。
なぜ過去問教材に「種類」があるのか?
一口に過去問集といっても、掲載年数や編集方針は大きく異なります。たとえば、
- 5年分掲載のもの
- 10年分掲載のもの
- 平成18年以降の全年度を収録したもの
- 「重要問題」のみを厳選したもの
といった具合に、教材の「量」と「質」はさまざまです。実はこれは、試験の出題傾向や効率的な学習とのバランスを取るための工夫でもあるのです。
【年数別】過去問集のメリット・デメリット
■5年分/10年分の年度別過去問集
近年の傾向をつかむには最適です。特に行政法などは、直近5年分の問題を参考にして作問されているとも言われています。したがって、本試験の「現在のレベル感」を知るうえでも、5年分は必ず解いておくべきです。
ただし、論点の網羅性には限界があります。たとえ10年分あっても、科目によっては重要論点がまったく扱われていないこともあります(特に民法)。
■平成18年以降の全年度収録型
論点の網羅性という意味では非常に優れています。特に行政法のように安定して出題される科目では、より深く理解できます。
ただし、分量が膨大で回転効率が落ちやすく、また難易度が高すぎる問題も含まれているため、全問に取り組むことが非効率になるケースもあります。
【結論】初学者・経験者のおすすめ過去問戦略
- 初学者 → 「重要過去問集」をベースに。余裕があれば5年〜10年分の年度別過去問を補完的に。
- 経験者 → 重要過去問集+すべての過去問(平成18年以降)を用い、知識の穴を潰す戦略が有効。
ただし、どの立場でも「直近5年分」は必ず解いておきたいところです。
過去問教材は「網羅性」×「効率性」のバランスが鍵
重要論点に絞った「厳選型過去問集」は、年度を問わず出題頻度の高い問題を抽出してくれており、最もコスパのよい教材と言えるでしょう。
さらに近年では、正答率の表示や重要度ランクの明示など、効率的な学習をサポートする工夫も進んでいます。市販教材を選ぶ際は、解説の質にも注意しましょう。
個別指導なら、さらに「あなた仕様」の教材選択が可能
もし自分に合った教材選びに不安がある場合、個別指導では科目別に適切な過去問教材の選定が可能です。
たとえば「行政法は全年度型で、民法は厳選型」といった科目ごとの使い分けもできます。解説のフォローや、間違えた問題の扱い方までサポートが入るので、教材の「使い方」まで指導を受けたい方には個別指導はおすすめです。
まとめ
行政書士試験における過去問は、単なる復習ツールではありません。「本試験の水準を知る」「出題傾向を掴む」「知識の穴を埋める」というすべての目的に直結する、極めて重要な教材です。
どの過去問教材を、どのように使うかで、合否を分けることすらあります。だからこそ、目的とレベルに応じた「選び方」が合格の鍵になります。
ぜひこの記事を参考に、自分に合った過去問戦略を立ててみてください。
【執筆者】
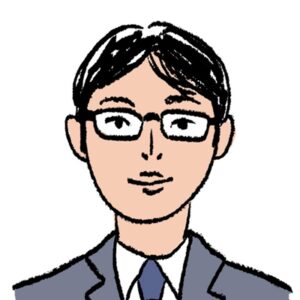
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
行政書士事務所を運営しながら、大手予備校で法律系国家試験の講師を20年間
担当してきました。法律について大学院で研究もしてきました。
「暗記より理解」が講師としての信条で、条文の理解のためならば、千年以上前
のローマの話もします。「法律の理解に資する方法を探す」ことを趣味としていて、
さまざまな文献に目を通します。蔵書は数百冊におよびます。








