ブログ
BLOG
何年も不合格…そんなあなたへ。突破の鍵は「司法試験式・個別指導」にあり
■努力しても報われない——そんな受験生を、私は見てきました<。
行政書士試験の受験指導に長年携わってきた中で、「模試では合格点なのに、本番では不合格が続く」という方に何人も出会いました。
知識も努力も十分。にもかかわらず、結果が出ない——その姿に、指導する私自身、胸が痛む思いでした。
こうした受験生の多くに共通していたのは、「表面的な理解はできているが、本質的な思考力や条文構造の理解が不十分」ということです。
では、どうすれば突破できるのか。
■ヒントは「簡単に受かってしまう」人たちにあった
行政書士試験に“簡単に”合格してしまう受験生がいます。それは、司法試験を目指す法科大学院生たちです。
彼らは、行政書士試験を“力試し”として受けることがあり、その多くが難なく合格していきます。
実は、行政書士試験と司法試験には深いつながりがあります。
試験委員の多くは司法試験の指導に携わる教授陣。
問題の傾向や価値観も、司法試験に似てくるのは必然です。
■だから私は、あえて「司法試験の教材」を使いました
本試験で伸び悩む生徒に対して、私はあえて司法試験向けの“基本書”を使って個別指導を行いました。
もちろん、行政書士試験に出ない内容は省き、民法の根幹的な考え方・条文構造・判例理論にフォーカス。
司法試験の世界に触れることで、問題の「出題意図」や「条文の使い方」が見えてくるようになります。
たとえば、知らない問題に出会っても、条文の構造から答えを導ける。
選択肢に迷っても、民法の価値観から絞り込める。
それができるようになった瞬間、合格への道が開けたのです。
■なぜ、私にはそれができるのか
私は、司法試験・行政書士試験の過去問研究、模試作成、民事法の研究にも携わってきました。
試験委員の論文にも目を通し、彼らの視点を分析してきました。
だからこそ、司法試験の基本書を「行政書士試験に合格するための教材」として使いこなせたのです。
■そして今、それをもっと自由に活かせる「個別指導」で
予備校のスクーリング授業では時間的制約がありましたが、個別指導ならば受講生のペースに合わせた密度の高い指導が可能です。
長年、不合格に苦しむ方にこそ、最も効果的なアプローチだと確信しています。
■模試では合格点。それでも本試験で落ち続けているあなたへ
「努力しているのに結果が出ない」「自分に何が足りないのか分からない」
そんな悩みを抱える社会人の方、一度、私たちの個別指導を体験してみませんか?
司法試験式・本質理解で、次はあなたが合格する番です。
【執筆者】
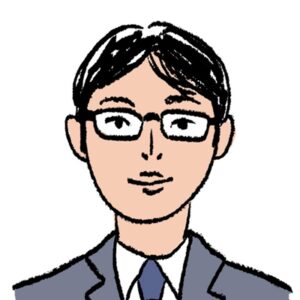
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
行政書士事務所を運営しながら、大手予備校で法律系国家試験の講師を20年間
担当してきました。法律について大学院で研究もしてきました。
「暗記より理解」が講師としての信条で、条文の理解のためならば、千年以上前
のローマの話もします。「法律の理解に資する方法を探す」ことを趣味としていて、
さまざまな文献に目を通します。蔵書は数百冊におよびます。








