インタビュー
INTERVIEW
A様・B様合格インタビュー
お名前
A様・B様
合格した大学
日本大学法学部公共政策学科・文理学部ドイツ文学科
出身高校
日本大学豊山女子高等学校
受験した年度
2025年度入試
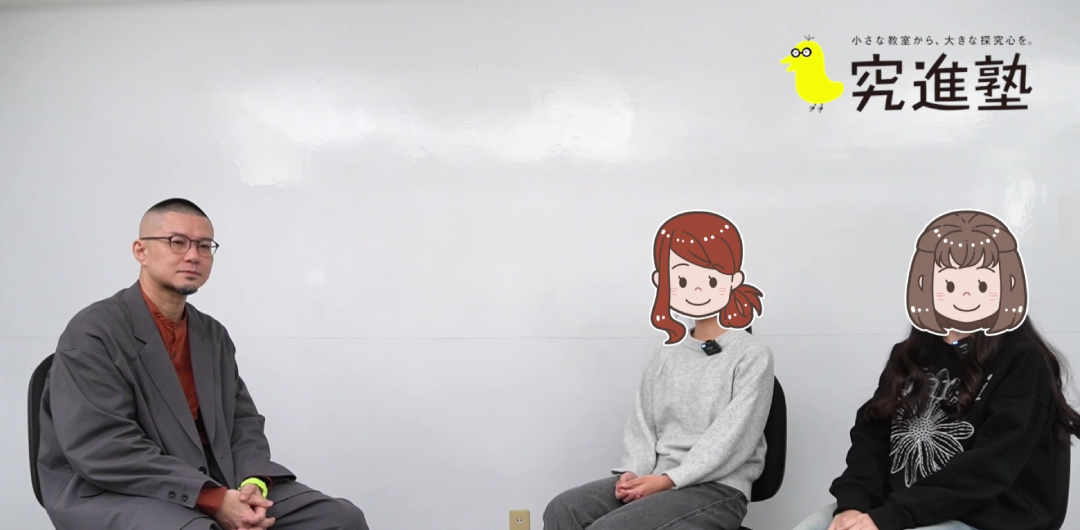
インタビューQ&A
粕川:究進塾に通う前と通い始めてから、どういうところで成長ができたと思いますか。
A:私は個別で数学の授業を取っていましたが、数学はもともとすごく苦手でした。計画を立てるのも苦手なのでどこから勉強していいか全然分からなかったのですが、塾に通ったことで自分の勉強が進めやすくなりました。
それから、勉強への意欲が増して自分から自習室に行こうと思えるようになったところも成長できた点だと思います。
B:私が基礎学の春期・夏期の講習を受けてみて思ったのは、小テストなどを通じて、国語だと四字熟語や漢字の苦手なところ、英語なら今まで理解してなかったところに気づくことができた点です。
北田:素晴らしい。模範的な解答ですね。
春期講習・夏期講習で印象に残ったこと
A:春期講習の時はたまたまこの2人だけで受けていました。なので、他の集団授業とは違って、知らない人と一緒ではなかったので、不安がある内容でも積極的に授業に参加できました。講座を通じて理解が深まったと思います。
粕川:究進塾で過ごしてきた期間の中で印象に残っていることはありますか?
A:大きく印象に残ってるのは春期講習と夏期講習のときです。普段は個別指導なので、辛いときも1人で黙々とやるしかなかったけれど、同じ目標に向かって頑張れる仲間ができました。そこで教え合ったりして、講習を受ける前よりも自分自身が成長できたと思います。
北田:Aさんは多分もともとものすごく物静かなタイプではないと思うし、個別でちゃんと集中して勉強するっていう形式はすごく大事だと思うけど、それだけになっている息苦しさや寂しさみたいなものがあったのかもしれないね。
一緒に勉強する仲間がいること
北田:集団授業は「こっちが喋って皆が聞くだけ」っていうスタイルではない形でやるようにしています。だから、受けてくれた皆がそこで色々発言してくれた。
休み時間は、必ず外に出て生徒同士でのコミュニケーションが取れるような時間を作ってたんだけど、帰ってみると皆が集まっていて、黒板に書きながら誰かが教えてたのが印象に残ってる。
個別指導主体ではあるけど横の繋がりがちゃんとできるというところは、今年はすごく良かったって感じましたね。
自分だけでやってるとつまらないし、特に試験前とか皆「あれがやばい」「これがやばい」ってテンパるからさ。それを自分の内だけにとどめないで済むというのはすごく良かったんじゃないかなって気がします。
B:塾に入ったときは、同じ学校の子がいない環境だったから寂しさもありました。一人で勉強しなきゃいけないみたいなのもあって。途中でAさんが合流してくれたから、今まで積極的に使っていなかった自習室を使いながら、基礎学前とかは特に一緒に教え合ったり、基礎学までのスケジュールを立てて一緒に頑張れたのがすごく良かったなと思っています。
北田:知ってる人と、またその友達がいることで動けたという部分はあると思うから、そういうのは本当に良かったよね。
A:究進塾では、授業外でも自習室を使えたり、参考書を自由に借りられるところがすごく良い環境でした。
北田:確かに本借りるのもいちいち申請しなきゃとかそういうの全然ないし、普通に「空いてる席自習で使って~」とかもあったし。その辺の気楽さみたいなのは行きやすいかもしれないね。
B:受付のスタッフの方の対応がすごく良いなって毎回思っていました。入った時に明るく挨拶してくれるっていうのがすごく嬉しくて、「勉強は嫌だな」って思って来たとしても「頑張ろう」って思えました。
北田:それは受付の皆さんもとても喜ぶと思います。
究進塾の特徴の一つに皆がとてもソフトっていうところがあって。例えば大手の有名なところとかに行くと、ちょっと軍隊っぽい「おはようございます!」と挨拶されたりするけど、ここは柔らかい方が多いから、朗らかに声かけてくれるし。他の受験生たちもよく言うんだけど、どうでもいい話もできるっていう。
もちろん、皆勉強しに来ているんだけど、それだけだと息が詰まるから、受付で世間話をしてるのも結構見るし、それがすごくいい息抜きになってるってよく聞くから。気軽に来れる塾っていうところはあるかもね。
基礎学力到達度テストを振り返って
A:今回うまくいったのが数学と選択科目の地理でした。数学は、本当に今まで苦手意識をずっと持ち続けていて、今までの基礎学でも全くいい点数を取れませんでした。でも、入塾してから担当してくださった吉田先生とすごく相性が合ったというか。私が分からないところも1から一緒に教えてくれたり、私に合ったプランを立てて教えてくださって、そのおかげで最後の基礎学で35点ぐらい点数が伸びたので、今までに経験したことないぐらい嬉しかったです。
A:地理は7月ぐらいにBさんと一緒に粕川先生のところに行って、地理の勉強法だったり参考書とかをどんなものを使ったらいいかを聞きに行きました。ただの相談だったのに真剣に「ここからこうしていった方がいいよ」っていう明確なプランまで立ててくださって。その日から参考書を買って、教えてくださった通りに頑張って計画的に進めたら、最後は結構納得できる点数が取れて。
北田:すごいよね。授業を担当してるとかじゃないもんね、粕川先生は。粕川先生は常にピシッとしたすごくちゃんとしたプリントとかを作って出してくれて。それに、それをきちんと実行したっていうのが素晴らしいよね。
北田:塾を一番最後に出ることも結構あって、そのぐらいの時間になるとあんまり人がいなくなったりするんだけど、ホワイトボードにどこかの地図みたいのが書いてあったりとか。2人がコソコソ喋ってるのを何回か聞いたけど、ずっと地理をやってたんだよね。なんとなく、最後は暗記科目を詰めようっていうのがすごく功を奏したのかなって気はするね。
必ずしも授業を担当してもらっていなくても、良い形で勉強をサポートしてもらえたっていうのはすごく良かったよね。
B:私も数学はうまくいきました。究進塾に入ったのが高1で、その時は中間テストとか期末テストが本当にできなくていろいろ対策していただいてたんですけど、やっていく中で数学の楽しさに気づくことができました。私が教えてくださった先生は基礎学前に、本当の基礎学にあったプレテストみたいな・・。
北田:あれ?2人は先生違ったの?
A・B:違いました。
北田:じゃあ、Bさんは高1から数学を受け始めたということね。
B:そうです。プレテストが2週間に1回ぐらいで、2ヶ月ぐらい続けてテスト慣れをしましょうってやってくださったんですけど、それで問題の傾向も掴めて、自分ができないところを分かったので基礎学でもいい感じにできたのかなって思ってます。
北田:素晴らしいね。
A:反対に、もう少し勉強しておけば良かったなって思ってる科目が英語で。どうしても数学や地理などに時間を取られてしまって。私は英文法が苦手だったんですけど、英文法や大事な単語にもう少し時間をかけれていたら絶対点数が伸びていたっていうのがありますね。
B:私もうまくいかなかったのは英語・・
北田:英語担当の僕がインタビューアーで良いんでしょうか(苦笑)
A・B:(笑)
北田:Aさんが言ってくれたことは、10年以上基礎学の対策を続けてるけど、毎年100%感じるところ。単語はみんな自分でできる、文法は一応高2までで勉強してるはずなんだけど・・夏期講習や春季講習は普段、塾に通っていない方もいっぱいいるから、「ここからやんなきゃか!」って毎年思う。
英語の方が他の科目よりも積み重ねでやらなきゃいけないところが多いから、そこをどう取り戻すかっていうところは難しいよね。
結局講習では、それぞれ「じゃあこうやって戦っていこう」っていう戦略や考え方の話を多くするけど、元々単語とか文法とかのベースがない状態で話されても「やり方は分かったけど文が読めない」みたいなことになっちゃう。そこがもっとうまくサポートできればっていうのはいつも思う。
B:私はもともと英語が得意な方ではなかったけど、今回基礎学を受けて一番ダメだったと思ったところは自分のやり方を貫きすぎてしまったことだと思っています。先生に教えてもらったことを実践しようと思っても、今までのやり方で解こうとしてしまったんです。新しいやり方をチャレンジするのがすごく難しかったです。
北田:でもそれを自覚できたってことは「勉強する」レベルは一歩上がったんだと思う。Bさんの性格的な面もあるのかなと思うし、そこを変えるにはもうちょっと時間はあったら良かったなっていうのも実際にはある。さっきも話したけど、解き方や考え方とかをきちんと習った経験がないという印象で。一本筋を通した解き方・考え方を身に着けてもらおうとやってきたけど、できた部分もあればできなかった部分もあったかな。
課題点も含めて、これから基礎学を受ける子たちは必ず参考になると思うから、話してくれてどうもありがとう。
授業は何のためにある?
北田:授業の最初に「授業って何のためにあるんだっけ?」って話したの覚えてる?10回ぐらい聞いたけど(笑)途中から、すぐ答えてくれるようになったじゃん。何だったか覚えてる?
A:自分の勉強をしやすくするため。
北田:そう、その通り。素晴らしい。例えば、普段全然塾に行ってない子だと「行ったら上がる」って思っちゃってる所があるけど、あくまで主人公は自分で、塾はサポート役に過ぎないから。勉強する方向性と、それを分かってても「全然問題解けない」だと手が進まないから、ちゃんと進められるようにモデルケースを授業で見せる。「はい、あとは自分でやって自分の力にして」っていう。そこは基礎学の皆に共通する課題の1つだと思う。そこを分かったうえで上手に授業を活用すること、あとは単純に1、2年生でやってたことを自分でもちょっとやっておくっていうのが後輩に向けて言えることかもしれないね。
A:はい。
どんな大学生活を送りたい?
A:私はまだ将来の夢が決まっていないのですが、スポーツが好きなのでサークルに入ってスポーツを楽しみたいです。あと勉強もですけど、大学に入ったら今よりいろんな人がいたりすると思うので、いろんな人と関わってみたいなって思います。
北田:素晴らしい。
B:私もサークルに入って楽しみたいのと、あとは言語系の学部に入ったので、その言語の資格を取って喋れるようになって海外旅行をしたいなって思います。
北田:何語を勉強されるのかな?
B:ドイツ語です。
北田:言語は違うけど、英語の勉強をしてたことは必ず役に立つと思うから。ドイツ語とかフランス語とか大学でやる子いるけど、「英語って簡単だったんだ!」って多分思うことになると思う。でも、さっき言ってくれた話もそうだけど、それが次の語学の勉強に必ず活きてくるから。
北田:普段の集団授業もそうだけど、「ここでやる知識がすごく大事」っていうよりも頭の使い方というか。目標・課題があって、いま自分がいる地点から、この期間で何をどうやったら近づけるかが大事で。そういうシミュレーションの具体例の一つとして英語を教えてた。
2人ともこれからたくさん遊ぶと思うけど、どっちにせよ勉強はどこかでしなきゃいけなくなる。そういうときに、基礎学を突破するまでの勉強が絶対役に立つから、そこで活かしてくれると良いなっていう感じです。
今までの学生生活とは違うことがたくさんあると思うから、その分自己責任でコントロールしなきゃいけないこともあるけど、是非良い4年間を過ごしてください。
A・B:はい。
後輩に向けてアドバイスをお願いします。
A:一番伝えたいのは、選択科目の勉強を早めに始めることだと思っています。今回の基礎学で選択科目がどれだけ大きな配点で大切かというのをすごく感じたし、範囲も広いので早めに取りかかって一通り早めに終わって、そこから過去問とかに入れるようにするのをお勧めします。
B:2年生の4月から、ちゃんとやっておいた方がいいなってすごく思いました。最後だけ良くても順位があまり上がらないことが結構あるので、早めの準備が必要かなと思います。
北田:同感です。一般受験じゃないっていうのももしかしたら影響してるのかもしれないけど、例年みんなギリギリで来すぎるっていう。
もちろんできることはあるけど、どうしたってある程度の蓄積が必要な部分があるから「もうちょっと前に始めてればな」って・・もちろん2人が話してくれたみたいに、ここに来て勉強の仕方が分かるとか仲間ができてモチベーションがあるとかそういうメリットが色々あると思うけど、でも自分でもできることって絶対あるから。
それをちょっとでも早い時期にやっておくだけで、だいぶ違うと思う。
終えた子がほぼ全員言うことだから、そこは本当に伝わるといいなと思います。
粕川:素晴らしいお話でした。ありがとうございます。





