ブログ
BLOG
行政書士の実務はどう学ぶ?合格後の「不安」を解消する4つの方法
行政書士試験に合格しても、多くの方が次のような不安を抱えています。
「実務ってどうやって覚えるの?」
「経験ゼロの自分でも、ちゃんと仕事ができるようになるのだろうか…」
この不安は当然です。
行政書士試験は実務を問う試験ではありませんし、合格後、すぐに現場で活躍できる保証はありません。
そこで今回は、実務を学ぶための具体的な4つの方法をご紹介します。
私自身の経験や、受講生・相談者の声も踏まえながらお話しします。
① 行政書士会による「公的研修」を活用する
最も信頼性が高く、体系的に実務を学べるのが、各都道府県の行政書士会が主催する研修です。
たとえば、東京都行政書士会では、新人登録者向けに新人研修が実施されています。
また、登録後は会員専用サイトから、業務別の動画研修をいつでも視聴可能。
講師は実務経験豊富な行政書士や、大学教授、行政機関の担当者など、多様な専門家が務めています。
多くの動画は無料で視聴可能(※一部、有料研修もあり)
自宅で視聴できるため、働きながらでも学びやすい
登録後でなければ利用できない点に注意
いわば、「もっとも安全で信頼性のある実務学習の場」と言えるでしょう。
② 民間の「私的研修会」に参加してみる
行政書士会主催ではない、各支部や任意の勉強会による私的な研修会も定期的に開催されています。
これらは、登録前の合格者でも参加可能な場合があります。
特に東京都行政書士会では、会報の後半に支部主催の研修情報が掲載されており、一般の方でも閲覧可能です(※ホームページをご確認ください)。
懇親会が開かれることもあり、人的ネットワークの構築に最適
参加費がかかることが多く(例:3000円程度)、事前確認が必要
情報収集と仲間づくりを兼ねた学習の場として、有効に活用できます。
③ 行政書士事務所で「働いて学ぶ」
一部の行政書士事務所では、合格者をインターンや補助者として受け入れているケースがあります。
現場で実務を学べる貴重な機会ではありますが、注意も必要です。
▼ 実際に寄せられた相談の例:
「実務を学びたかったのに、雑用だけで終わってしまった…」
「教えるという名目で高額な教材を買わされた…」
このように、労働力として利用されるリスクや、悪質な勧誘被害も一部に見られます。
事前に事務所の評判や契約内容をよく確認し、慎重に選ぶようにしてください。
④ 書籍・動画で「独学する」
行政書士向けの実務書籍は、近年かなり充実してきています。
特に、建設業許可・相続・法人設立など、代表的な業務分野では良書が多数出版されています。
書籍は監修が入り信頼性が高く、体系的に学びやすい
興味のある業務分野が決まっている方に特におすすめ
また、最近ではYouTube等で実務に関する解説動画も多数公開されています。
ただし、動画については発信者の実績や内容の正確性に注意しましょう。
まとめ:自分に合った方法で、実務を一歩ずつ学ぼう
| 学び方 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| ①行政書士会の研修 | 登録者限定/動画視聴可 | 信頼性が高い/体系的 | 登録しないと利用不可 |
| ②私的研修会 | 支部や任意団体が主催 | 参加しやすい/人脈ができる | 費用あり/質にばらつき |
| ③事務所で働く | 現場で実務を体験 | 実践的に学べる | 搾取やトラブルの可能性 |
| ④書籍・動画で学習 | 自分のペースで学べる | 分野を絞って学習可 | 信頼性の見極めが必要 |
実務の学び方に「これ一つが正解」というものはありません。
あなたのライフスタイルや性格、目指す業務分野に合わせて、上手に組み合わせて活用してみてください。
行政書士としての一歩を、確実なものにしていきましょう。
【執筆者】
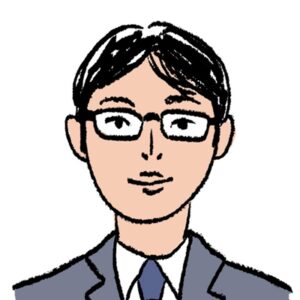
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
行政書士事務所を運営しながら、大手予備校で法律系国家試験の講師を20年間
担当してきました。法律について大学院で研究もしてきました。
「暗記より理解」が講師としての信条で、条文の理解のためならば、千年以上前
のローマの話もします。「法律の理解に資する方法を探す」ことを趣味としていて、
さまざまな文献に目を通します。蔵書は数百冊におよびます。








