ブログ
BLOG
「図表」は最強の武器──行政書士試験における学習効率を最大化する方法
行政書士試験では、各科目において“比較”を問う問題が頻出します。たとえば行政法では「行政不服審査法」と「行政事件訴訟法」の違い、民法では「地上権」と「賃借権」の比較といった具合です。これらの比較論点は、過去問でも繰り返し問われており、いわば“鉄板テーマ”です。
このような重要論点に対応するために、予備校のテキストには図表が豊富に掲載されています。図表は情報を一目で把握できる「一覧性」に優れており、特に比較問題の理解と記憶には抜群の効果を発揮します。
ところが、私がこれまで見てきた多くの受験生は、この図表を十分に活用できていません。ただ眺めるだけ、あるいは読み流すだけで終わっているのです。これは、非常にもったいないことです。
断言します。
もし「行政法を15分で復習せよ」と言われたら、私なら図表だけを見ます。
それだけ、図表には試験に直結するエッセンスが凝縮されているのです。
効率を最大化する「図表学習法」──4つのステップ
① 図表目次を自作する
まず最初に取り組んでいただきたいのは、図表の目次を自分で作ることです。
行政書士試験のテキストには、図表が散在していて全体を把握しにくいという欠点があります。だからこそ、自分で図表の一覧を作成することで、「どの論点が、どこで扱われているのか」を俯瞰できるようになります。
目次は、手書きよりも**データ化(Excelやメモアプリ等)**がおすすめです。音声入力などを使えば、作成もスムーズに行えるでしょう。
② 比較項目数を目次に記載する
次に、図表目次に**「比較対象の数」**を書き加えてみてください。
例えば、「地上権と賃借権の比較」図表に5つの項目があるなら、「対象数:5」と記載します。これだけで、目次を見た瞬間に頭の中で「何が比較されていたか?」を思い出す訓練になります。
単に図表を眺めるだけでは、「思い出す力(想起)」は鍛えられません。目次ベースのトレーニングは、記憶のアウトプットを促す極めて効果的な方法です。思い出せなかった内容には×印をつけ、重点的に復習しましょう。
③ 理解のポイントを図表に書き込む
図表を「覚える」のではなく、「理解する」ために、各比較の本質的な違いを一言で記載しましょう。
例えば、「地上権と賃貸借の比較」なら、「物権と債権の違いが軸」という理解の視点を添えます。
この“理解の軸”があるだけで、暗記の負担は大きく軽減されます。記憶は「意味」を伴うことで定着しやすくなります。これは、単なるテクニックではなく、講師として伝えるべき学習の核心です。
④ 出題実績を追記する
さらにステップアップしたい方は、図表に過去問の出題実績をメモしましょう。
「R5-25-1」のように年度と問題番号を記載し、「どう問われ、どう引っかけられたか」まで加えておくと、試験委員の意図が見えてきます。
こうすることで、図表は単なる“まとめ”から“得点直結ツール”へと進化します。
まとめ:図表を「見る」だけでは、力はつかない
図表は“最短で得点力を伸ばす武器”です。
しかし、それは正しく使いこなしてこそ意味を持ちます。目次の作成、比較項目の把握、理解の視点、出題実績の追記——この4ステップを通じて、図表をあなた自身の学習戦略の中核に据えてください。
この方法を習慣化できれば、行政書士試験における“比較問題”は、確実に得点源になります。
そして何より、「自分で作った知識の地図」を持つことは、学習への自信と手応えにつながります。
【執筆者】
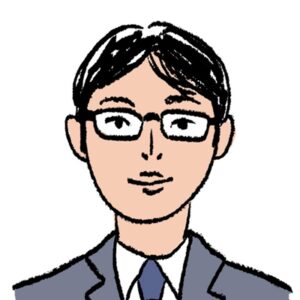
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
行政書士事務所を運営しながら、大手予備校で法律系国家試験の講師を20年間
担当してきました。法律について大学院で研究もしてきました。
「暗記より理解」が講師としての信条で、条文の理解のためならば、千年以上前
のローマの話もします。「法律の理解に資する方法を探す」ことを趣味としていて、
さまざまな文献に目を通します。蔵書は数百冊におよびます。








