ブログ
BLOG
行政書士試験の「教材選び」で、遠回りしていませんか?
社会人が行政書士試験に挑戦するうえで、限られた時間を有効に使うには、最初の教材選びが合否を左右すると言っても過言ではありません。
とはいえ、本屋に並ぶ大量の参考書、ネットで紹介される無数の教材…。一体どれを選べばいいのか、迷ってしまう方も多いでしょう。
そこで今回は、予備校での指導経験をもとに、教材の“つくられ方”と“選び方”のポイントをわかりやすく解説します。
教材はすべて「過去問」がベース。でも…
実は、ほとんどの教材は同じ「過去問」をもとに作られています。それなのに、なぜ内容にこんなにも差が出るのでしょうか?
理由の一つは、過去問の選別基準にあります。
- 出題回数の多い問題を重視する教材
- 正答率の低い問題を重点的に解説する教材
- 10年分重視か、直近5年重視か
このように、同じ素材を使っていても、編集方針次第で教材の構成は大きく変わるのです。
発展的内容の扱いも、教材ごとに違います
行政書士試験では出題されていないものの、司法試験・予備試験・司法書士試験などで頻出の論点を取り入れた教材もあります。
これらは予想問題として有効ですが、内容が高度になる分、学習の負担も増します。
教材によって「どこまで深堀りするか」の方針が違うため、自分のレベルや目的に合っているかを見極める必要があります。
表現形式にも要注意。「図表型」か「文章型」か?
教材の“見せ方”も重要なポイントです。
図解が豊富で視覚的に理解しやすいタイプか、文章中心で論理的に解説されているタイプか。
また、横断的なまとめ方や索引の充実度なども、学習効率に直結します。
ご自身が「図で理解したい派」か「読んで覚える派」かによって、相性の良い教材はまったく異なります。
個別指導なら、教材選びから伴走します
市販教材を自由に選べる個別指導では、「最適な教材」を一緒に探し、必要に応じて使い分けながら指導していきます。
例えば…
- 文章より図解の方が頭に入りやすい → 図表中心の教材を
- 過去問を解いたが手ごたえが悪い → 解説が詳しいタイプに変更
- 時間がない → 最短ルートの教材だけに絞る
教材選びで悩む時間を、合格への学習時間に変える。
それが、個別指導の価値のひとつです。
【執筆者】
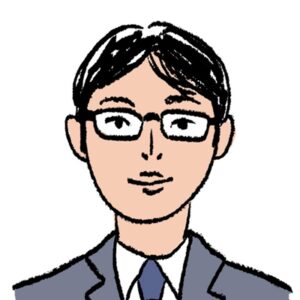
Y(イニシャル表記)
究進塾の行政書士コースの担当講師。
国立大学大学院修士課程修了。
私立大学非常勤講師の経験を持ち、大手資格予備校で行政書士をはじめとする法律系国家資格の指導歴は約20年。
行政書士実務についての著書・論文もあります。
<塾よりひとこと>
誠実で実直な性格が特長の講師です。








